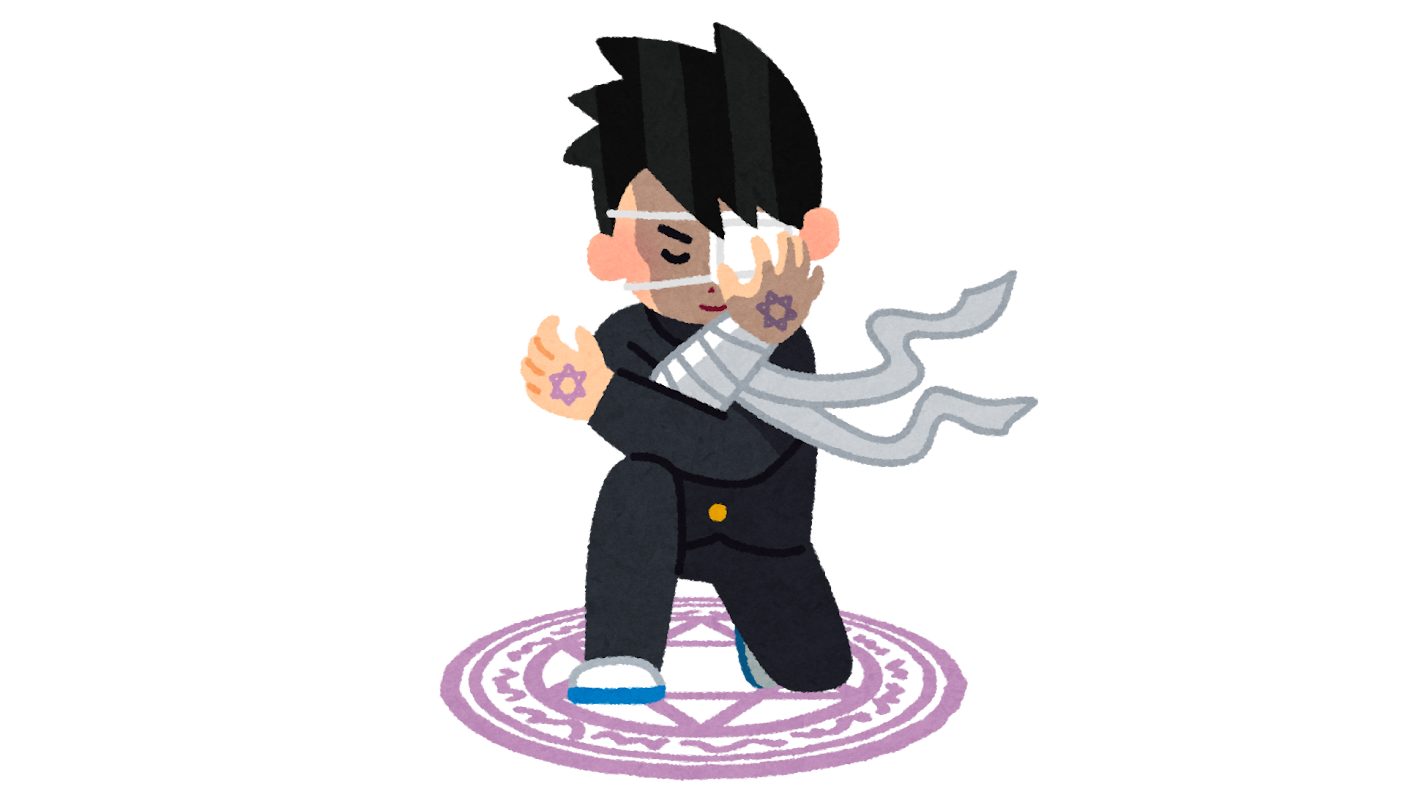Written by 白子
第一章:偏頭痛と移行
田中健二(たなかけんじ)、45歳、某市役所会計課係長。彼の世界は、蛍光灯の白々しい光と、積み上げられた書類の灰色、そして時折響く市民からの苦情電話の不協和音で構成されていた。その日も、彼は「都市計画区域内における建築物の形態意匠に関する指導要綱(改訂版)草案」の条文と格闘していた。複雑怪奇な文言、参照先の多さ、そして何より、この書類が最終的に誰の役に立つのかという根源的な疑問。それが、彼の日常だった。
午後3時14分。突如、こめかみに鋭い痛みが走った。いつもの偏頭痛か、と田中は思った。だが、痛みは引くどころか増していく。視界が歪み、蛍光灯の光が虹色のにじみを見せ始めた。机の上の書類の文字が、意味不明な記号の羅列に見えてくる。耳鳴りがひどい。まるで、古いラジオのチューニングが狂ったような、断続的なノイズ。
「……大丈夫ですか、係長?」
部下の声が、やけに遠く聞こえる。返事をしようとしたが、声が出ない。視界が明滅し、足元の感覚が薄れていく。これは、いつもの偏頭痛ではない。何かが、おかしい。彼は椅子から崩れ落ちるように床に手をついた。床のタイル模様が、ぐにゃりと歪んで見える。世界が、まるで安物の万華鏡のように、ゆっくりと、しかし確実に変容していく感覚。トラックにはねられるような衝撃も、神々しい光もなかった。ただ、不快な浮遊感と、方向感覚の喪失だけが、じわじわと彼を侵食していった。
どれくらいの時間が経ったのか。次に彼が意識を取り戻した時、そこは見慣れた市役所の床ではなかった。硬く、冷たく、奇妙な模様が刻まれた石畳の上だった。周囲には、見たこともない形状の建物が、非ユークリッド的な角度で林立している。空の色は鈍い鉛色で、空気は硫黄と埃の混じったような匂いがした。
彼の傍らには、例の「指導要綱(改訂版)草案」がぎっしり詰まった、くたびれたブリーフケースだけが転がっていた。
第二章:ヴェリディウムの洗礼
田中は混乱していた。ここはどこだ? 誘拐か? それにしては、周囲には人通りがある。だが、その人々も奇妙だった。服装は統一性がなく、継ぎはぎだらけの者もいれば、妙に豪奢な装飾をつけた者もいる。そして、彼らが話す言葉は、全く理解できなかった。日本語ではない。英語でも、中国語でもない。まるで、複数の言語を無理やり繋ぎ合わせたような、奇妙な響きを持っていた。
彼は立ち上がり、周囲を見渡した。巨大な建造物が空を突き刺すように聳え立ち、それらの間を、蒸気を噴き出すパイプや、用途不明の歯車が複雑に絡み合いながら走っている。地熱を利用しているのか、時折、地面の亀裂から白い蒸気が噴き出していた。しかし、その一方で、建物の窓は煤けて薄汚れ、道端にはゴミが散乱している。技術レベルがちぐはぐで、統一感がない。
彼は誰かに助けを求めようとしたが、言葉が通じない。身振り手振りで何かを伝えようとしても、怪訝な顔をされるか、無視されるだけだった。彼は完全に孤立していた。チート能力など、どこにもない。あるのは、45年間の人生で培った中年の体力と、老眼気味の視力、そして日本の地方自治体の条例に関する無用な知識だけだ。
空腹を感じ始めた。最後に食事をしたのはいつだったか。財布は持っているが、日本の円がここで通用するとは思えない。彼は絶望的な気分で、この巨大で不条理な都市――後に彼が「ヴェリディウム」という名だと知る――を彷徨い始めた。彼の目標は、魔王討伐でも世界征服でもない。ただ、今日を生き延びること。そして、できれば元の世界に帰る方法を見つけること。それだけだった。
第三章:書式B-7を求めて
数日が経過した。田中は、ゴミ箱を漁って見つけた残飯と、公園らしき場所の噴水(水質は不明だが、他に選択肢はなかった)で飢えと渇きを凌いでいた。幸い、季節は寒くも暑くもないようだったが、夜は石畳の冷たさが身に染みた。
彼は、この都市のシステムを理解しようと試みた。観察するうちに、人々が特定の建物に頻繁に出入りしていることに気づいた。そこには、理解不能な文字で書かれた看板が掲げられていたが、人々が手にしている書類の束から、何らかの役所のような場所だろうと推測した。彼は、生存のためには、この都市のシステム――官僚機構――と関わらざるを得ないことを悟った。
彼は、見様見真似でいくつかの単語を覚えた。「許可」「申請」「食料」といった、生存に直結しそうな言葉だ。そして、意を決して、最も人の出入りが多い建物――市民維持局(第七G分署)と彼が勝手に名付けた――の扉をくぐった。
内部は、想像を絶する混沌だった。無数の窓口があり、それぞれに長蛇の列ができている。人々は怒鳴り合い、職員は無気力な表情で判を押している。空気は淀み、紙とインクと人いきれの匂いが充満していた。
田中は、最も列の短い窓口に並んだ。数時間後、ようやく彼の番が来た。彼は覚えたての単語を並べ、身振り手振りを交えて「食料」と「滞在許可」を求めた。窓口の職員――性別も年齢も判然としない、無表情な人物――は、田中の言葉を意にも介さず、一枚の書類を突き出した。そこには、やはり理解不能な文字がびっしりと書かれていた。
職員は、書類のある箇所を指差し、何かを早口でまくし立てた。田中が困惑していると、隣の窓口の職員が、面倒くさそうに「書式B-7、戸籍確認省、捺印」とだけ、比較的わかりやすい発音で教えてくれた。
どうやら、この書類を完成させるには、まず別の役所(戸籍確認省?)で「書式B-7」なるものを手に入れ、捺印をもらってくる必要があるらしい。田中は、空腹と疲労で眩暈を感じながら、礼を言ってその場を後にした。冒険者ギルドも、レベルアップもない。ただ、終わりの見えない bureaucraticな手続きだけが、彼の前途に横たわっていた。
第四章:堂々巡り
翌日、田中は道行く人に「戸籍確認省」の場所を尋ね歩いた。幸運にも、身振り手振りで場所を教えてくれる親切な(あるいは、単に暇だったのかもしれない)老人がいた。半日かけてたどり着いた「戸籍確認省」は、市民維持局以上に混沌とした場所だった。
彼は再び数時間待ち、ようやく窓口にたどり着いた。震える手で、昨日市民維持局でもらった書類を見せ、「書式B-7」と呟いた。窓口の職員は、書類を一瞥すると、別の書類の束から一枚抜き取り、田中に渡した。これが書式B-7らしい。しかし、職員は首を横に振り、別の窓口を指差した。どうやら、捺印は別の場所で貰う必要があるようだ。
田中は、指示された「捺印課」と思われる窓口に並び直した。さらに数時間後、彼の番が来た。彼は書式B-7を差し出した。捺印課の職員は、書類を受け取ると、虫眼鏡のようなもので隅々まで確認し、やがて何かを書き込むための別の書類――「書式C-12」と上部に書かれているように見えた――を要求した。
「書式C-12? それはどこで?」
田中が必死に尋ねると、職員は面倒くさそうに「エネルギー使用遵守局」とだけ答えた。
田中は、その日は諦めて宿(と呼べる代物ではないが、雨風をしのげる廃墟)に戻った。翌日、彼は「エネルギー使用遵守局」を探し出し、書式C-12を申請した。そこでは、彼の「エネルギー使用状況」に関する証明が必要だと言われた。もちろん、そんなものはない。彼は途方に暮れた。
数日後、彼は再び市民維持局(第七G分署)の最初の窓口に立っていた。奇跡的に、彼はなんとか「書式B-7」に捺印をもらうことができたのだ(どうやって? それは彼自身にもよくわからなかった。おそらく、いくつかの窓口で賄賂代わりにブリーフケースに入っていたボールペンを渡したのが功を奏したのかもしれない)。
しかし、窓口にいたのは、前回とは別の職員だった。田中が意気揚々と捺印済みの書式B-7を提出すると、職員は眉をひそめ、こう言った。
「この書式は昨日廃止されました。現在は書式B-8が必要です。申請には、反体制カルトとの無関係証明書を添付してください。それは、都市の反対側にある県保安局で、隔週木曜日にのみ発行されます」
田中は、その場で膝から崩れ落ちそうになった。彼のブリーフケースに入っている日本の地方自治体の条例は、この不条理な迷宮の前では何の役にも立たなかった。英雄的な活躍も、美少女との出会いもない。ただ、空腹と、絶望的なまでの徒労感だけが、彼を打ちのめしていた。彼は、今日もまた、ゴミ箱を漁ることから一日を始めなければならないのだろうか。ヴェリディウムの鉛色の空の下で、彼の異世界生活は、テンプレートとは程遠い、地味で、そして果てしなく続くかのように思われる苦闘の中にあった。